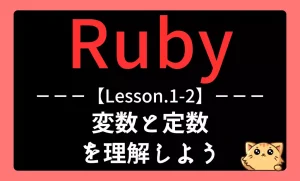【Ruby】Lesson1-1|Rubyの入り口|初めてコードを書いてみよう
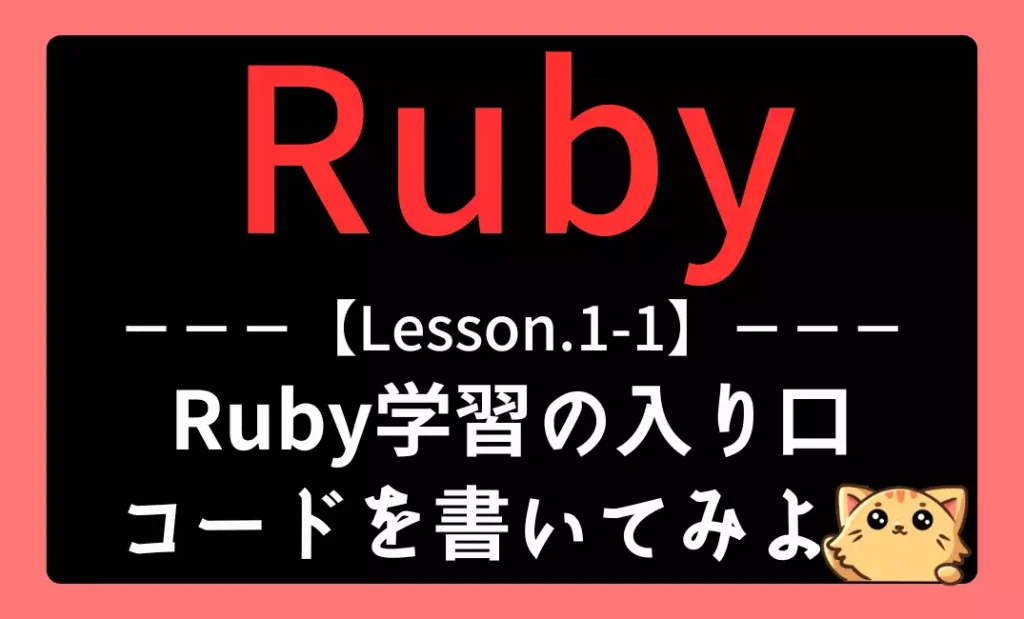
プログラミングを始めるにあたって、最初に覚えるべき基本操作として「入力」と「出力」があります。
ユーザーからデータを受け取る「入力」と、プログラムの結果を画面に表示する「出力」は、プログラムの最も基本的な動作です。
またプログラムの各部分に「コメント」を書き込むことで、コードがどのように動作するかを記述し、理解しやすくすることができます。
本記事では、Ruby学習の最初の一歩として、これらの基本について解説します。
Lesson1:基礎文法編
・Lesson1-1:Ruby学習の入り口|初めてコードを書いてみよう ◁今回はココ
・Lesson1-2:変数と定数を理解しよう
・Lesson1-3:四則演算をしよう
・Lesson1-4:文字列を操作しよう
・Lesson1-5:乱数を生成しよう
・確認問題1-☆1:ランダムパスワードを生成しよう
Lesson2:制御構造編
Lesson3:メソッド編
Lesson4:コレクション編
Lesson5:オブジェクト指向編
Rubyの入り口|入出力とコメントの書き方を学ぼう
まずは、分かりやすい「出力」から先に見ていきましょう。

ふたつの出力|putsとprintの使い方と違い
「出力」とはプログラムが処理したデータやメッセージを画面に表示する操作のことです。
計算の結果やユーザーへのメッセージなどを表示することで、プログラムがどのような動作をしたのかを目で確認できます。
Rubyで画面に出力するには、putsメソッド または printメソッド を使います。これらはどちらも画面にデータを表示しますが、少し違いがあります。
putsメソッドputsは指定した内容を画面に表示した後、自動的に改行を入れます。printメソッドprintは指定した内容を表示しますが改行は入れません。続けて出力を表示する場合、次の出力が同じ行に続きます。
実際にコードを書いて確認してみましょう。
行頭にputsメソッドやprintメソッドを書き、半角スペースの後に2つのダブルクォーテーションと、その間に出力したいメッセージを書きます。
puts "Hello, Ruby!" print "これはprintメソッド。" print " 改行されません。"
このコードを実行すると、画面には以下のように出力されます。
Hello, Ruby! これはprintメソッド。 改行されません。
このように、putsとprintは使い方によって表示のされ方に違いがあるため、場面に応じて使い分けることが大切です。
ユーザーからの入力を受け取る方法|getsメソッドの使い方
「入力」とは、プログラムにデータを提供することを指します。
ユーザーが入力した情報をプログラムが受け取り、それを基に処理を進めることで、プログラムに柔軟性が生まれます。
Rubyではユーザーからの入力を受け取るために getsメソッド を使用します。
getsはユーザーがキーボードから入力した情報を取得し、そのままプログラム内で利用できるようにします。
getsで取得した内容は「変数」というデータの保管箱に保存しますが、変数の詳細についてはLesson1-2で詳しく解説します。
今の時点では、「とにかくgetsメソッドで取得したデータが変数の中に入る」と思っておけば問題ありません。
print "お名前を入力してください:" name = gets print "こんにちは、" print name print "さん!"
このコードでは「お名前を入力してください:」と出力したあと、「name = gets」の部分で入力が行われます。
この「name」が変数であり、「gets」によってユーザーが入力したデータがnameという箱に入ります。
上記のコードを実行すると、まずは以下のように出力されます。
お名前を入力してください:
「お名前を入力してください:」を出力し、ユーザーからの入力を待っている状態です。
ここでターミナルに直接「太郎」と入力すると以下のように出力されます。
お名前を入力してください:太郎 こんにちは、太郎 さん!
このように、getsによってユーザーが入力したデータが変数nameに格納され、それがprintを用いて出力されました。
この例ではprintメソッドで出力しているにも関わらず「太郎」の後で改行されてしまっていますが、これは変数の特性によるものです。Lesson1-2で解説しますので、ここでは気にせず進めましょう。
このように入力と出力を上手に組み合わせることで、インタラクティブなプログラムが作成できます。
また、変数nameを出力する際にはダブルクォーテーションが不要であることも覚えておきましょう。
コメントの書き方と使いどころ
「コメント」はプログラム内にメモを残すための記述です。
コード内にコメントを追加することで、コードの内容を他の開発者や将来の自分が理解しやすくなります。
コメントはプログラムの動作に影響を与えないため、自由に記述が可能です。
コメントの基本文法
Rubyでは「#記号」を使うことでプログラム内にコメントを挿入できます。
「#」以降の文字列はプログラムの実行時に無視されます。
# ここからプログラムが開始します puts "Hello, World!" # putsメソッドで画面にメッセージを表示 # 次にユーザーからの入力を受け取ります print "お名前を入力してください:" name = gets # 名前の入力 print "こんにちは、" # ここから3行かけてあいさつを出力 print name print "さん!"
このように、コメントを使用することでプログラムの内容がわかりやすくなり、コードの意図や動作が明確になります。
複数行コメント
複数行に渡るコメントを書くときは、「=begin」と「=end」キーワードを使って記述できます。
次のように囲まれた部分がコメントになります。
=begin ここは複数行コメントです。 好きなだけ行を追加できます。 =end puts "ここはコードです"
注意: =begin と =end は必ず行の先頭に記述する必要があります。また行頭のインデント(半角スペース)があるとエラーが発生するため、注意が必要です。
ただし、# を全ての行頭におく書き方でも当然問題なく、こちらの方がより一般的です。
まとめ|Ruby学習の第一歩
今回はRuby学習の第一歩として、「入力」「出力」「コメント」について学びました。
これらの機能はプログラムの基本ですが、非常に重要な要素です。
次回は「変数と定数」について解説し、入力されたデータを保存して利用する方法を学びます。
引き続き、基礎をしっかり身につけていきましょう。
練習問題|自己紹介プログラムを作成しよう

Rubyの基礎をしっかりと身に着けるため、練習問題に挑戦しましょう。
自己紹介プログラムを作成しよう
簡単な自己紹介プログラムを作成しましょう。
またプログラム内にはコメントを書いて、何をしているコードなのか分かるようにしてください。
- ユーザーに名前を尋ね、その入力を受け取ること。
- 入力された名前を使って、自己紹介の文章を出力すること。
- コード内には、何をしているかを説明するコメントを適切に追加すること。
ただし、以下のような実行結果となるコードを書くこと。
名前を入力してください: 田中 はじめまして。私は田中 です。 よろしくお願いします。
この問題の解答例と解説
この問題の正解コードとその解説は以下の通りです。
クリックして開いて確認してください。
- 正解コード
-
# 名前の入力を促す print "名前を入力してください: " # ユーザーの入力を取得し、変数 name に格納 name = gets # メッセージを出力 print "はじめまして。私は" print name puts "です。" puts "よろしくお願いします。"
- 正解コードの解説
-
非常に基本的な問題のため解説はありません。
難しいと感じる場合はページ上部の解説を読み返しましょう。
FAQ|Rubyの出力・入力・コメントに関する基本疑問
- Q1. putsとprintの違いは何ですか?使い分ける場面の目安は?
-
putsは出力後に自動で改行しますが、printは改行しません。複数行を見やすく表示したいときはputs、同じ行で続けて出力したいときはprintを使うのが一般的です。
- Q2. getsで取得した入力に改行が含まれるのはなぜ?どう処理すればいい?
-
getsは入力の末尾に改行文字(\n)を含んだまま取得します。これを削除するには
chompメソッドを使います。例:name = gets.chomp。
- Q3. コメントはどのような場面で活用すべきですか?
-
コメントはコードの目的や処理の意図を明確にしたいときに使用します。特に他人との共同開発や、数カ月後に自分が見返す可能性のあるコードには、積極的にコメントを付けると可読性が向上します。